チラシ業界の実態
さて、前のページでは「ポスティングで大きな利益を生むのは併配である」と書いてきましたが、併配は複数のチラシの配布エリアが合致しなければならず、同業者同士の競争も激しくなってきて一つの業者が受ける依頼も少なくなってきていますし、チラシの配布期限なども影響して、1部での配布を余儀なくされる場合も多々あります。
1部での配布は配布スタッフに支払う報酬の比率が高くなり利益は少なくなりますし、そこに会社内部の事務費、配送にかかる人件費やガソリン代、車の維持費などが必要になるため下手をすれば赤字になりかねません。
そうなると1部での配布でも出来るだけ利益を確保する方法が必要になります。
どうすれば一番利益が出るのか?
答えは単純、依頼を受けたチラシを配布しなければいいのです。
ただし全く配布しなければすぐに依頼主にバレてしまいますから、8割~9割配布して残りの1割~2割はヒッソリと捨てます。
前のページで10000部の依頼を単価4円で受け、配布スタッフに単価3円で配らせた場合の例を挙げました。
その場合は経費を除く利益は10000円ですが、これを8割…つまり8000部の配布に留めたらどうなるでしょう?
10000部×4円=40000円
8000部×3円=24000円
40000円-24000円=16000円
8割に抑えると100%配布した場合に比べ上記のように6000円もの利益が上乗せされます。
つまり配布しない2000部の売り上げは丸儲けという事になるのです。
ここで一つ疑問になるのが「8割9割の配布で依頼主にバレないの?」という事だと思います。
答えは…
ほぼバレません。
8割9割配布すれば大半の家には配布されることになり、依頼主がちょっとチェックしたくらいで見抜くのは困難です。
仮に依頼主の会社のスタッフが住んでいる家にチラシが入らずクレームが来たとしても、「たまたま入らなかった」「チラシを配りきってその周辺には入れられなかった」などの言い訳ができ、なおかつ大半の家には入っている訳ですから「気になるのであれば別の所をチェックしてみて下さい」という強気の発言も出来ます。
この仕組み、何かに似ていると思いませんか?
そう、前半で説明した新聞の押し紙問題です。
新聞の押し紙問題は、販売店が押し紙分も配達部数に入れ部数を水増しし、水増しした分の折り込みチラシの収入を不正に得ているというものですが、これはつまり4000部の折り込み依頼を受けたけど、実際の配達部数は3000部なので1000部分のチラシ収入は丸儲けという事。
どちらも依頼された部数に対して配達部数を減らし、減らした分のチラシの売り上げをすべて利益に変えてしまうという点は完全に共通します。
ちなみに新聞折り込みなら押し紙の水増し分チラシの配達部数は減りますが、水増し分以外はほぼ確実に折り込みに組み込まれ配達されますが、ポスティングの場合は上記の業者自体の不正もさることながら、配布スタッフの不正(配布せずに捨ててしまうetc…)なども排除できず、どの程度配布されるかは不透明と言わざるを得ません。
どちらにせよチラシ業界の末端である新聞折り込みやポスティングで100%の配達、配布を期待するのは難しいという事です。
もしこれを見ている方が依頼主の立場になる場合の対処法としては、新聞折り込みなら販売店の言う配達部数の7~8割程度の折り込み依頼に留める事(5000部と言われたら3500~4000部の依頼)。
ポスティングであれば事前に厳しくチェックする事を業者に伝え牽制しておき、複数回依頼するのであれば実際に多少のチェックを行い、チェックした事を業者に伝える。
本来なら依頼主がこんな対策を打たなくてもシッカリ配達、配布するべきなんですがね。
あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
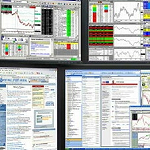
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
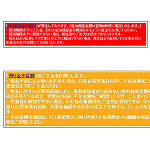
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む
