デフレーションとは
前ページの「インフレーション」に続いてデフレーションについて解説していきます。
デフレとは「物価の上昇=貨幣価値の下落」であるインフレの逆で「物価の下落=貨幣価値の上昇」になります。
一般的に経済などのニュースでよく耳にするのは「インフレ」という言葉ですが、日本においてはちょっと事情が違い「デフレ」という言葉をよく耳にする事でしょう。
というのも日本ではバブル崩壊後デフレに苦しめられてきたからです。
戦後G7などの先進国でデフレに陥った国は日本だけで、多くの国々はインフレを押さえ込むために苦慮しているのですが、日本はデフレ脱却に苦慮している状況で、2011年10月現在デフレ脱却には至っていません。
ではなぜデフレになるのか日本を元に考えてみましょう。
これもインフレ同様様々な要因があるのですが、まず単純にインフレの逆で考えてみると、
需要が供給を上回りインフレになるのであれば、供給が需要を上回ればデフレになる。
つまり「物あまり」の状況という事になりますが、今の日本の消費の弱さを考えるとこれは妥当な考えと言えます。
もう一つのインフレの原因である人件費、原材料高によるものでデフレを考えると、少なくとも今の日本の賃金は下落、横ばい傾向なので人件費の面でいえばデフレに結びつくかもしれませんが、大豆や小麦粉、原油などの様々な原材料は概ね高騰しており、むしろインフレ圧力が強まってもおかしくない状況です。
それでもデフレ脱却に手間取っているのは、やはり消費の弱さが一番の要因で、そこからもたらされる「デフレスパイラル」から未だに抜け出せない…と考えるのが妥当なのでしょうか。
ちなみにデフレスパイラルとは下記のような悪循環を指します↓
1・供給が需要を上回り物が余るので物価が安くなる
↓
2・物価が安くなれば企業の売り上げも減り業績は悪化
↓
3・企業の業績が悪くなると従業員の賃金は減り、雇用も悪化する
↓
4・企業は業績の悪化により設備投資を控え、給与所得者は賃金の減少により消費を控える
↓
5・物が売れなくなる ※以下1へ戻る
一説には高齢化と人口減少が大きな原因と見る動きもあります。
しかし実際に人口が減少に転じているドイツなどの東欧、ロシアなどでもデフレには陥っておらず、ある程度の要因にはなりえても直接的かつ大きな原因とは考えにくい。
まあこの辺を突き詰めるとキリがないので別のページでじっくりやりたいと思います。
インフレの場合「年1~2%の緩やかなインフレが理想的」と言われ、必ずしも悪いものではありませんが、デフレの場合あまりメリットは無く悪い面が目立ちます。
あえて言うなら借金大国の日本においてはデフレのお陰で実質金利は上がらず、膨大な金利の支払いを最低限に抑えられているという点か。
そもそもデフレには多くの場合弱い消費が付きまとうので、経済活動はどうあっても弱くなる。
「物が安くなった」と喜んでいる人は、それによって企業や従業員、ひいては日本自体にどういった事が起きるのかまで想像できない人と言わざるを得ない。
目先の微妙な物価安など吹き飛ぶくらいの損が中長期的に回りまわって自分に降りかかってくる…それがデフレというものだと覚えておきましょう。
あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
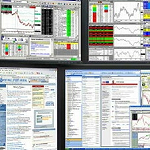
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
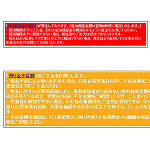
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む
