特定口座の源泉徴収ありとなしの違い
一般口座と特定口座の大きな違いは年間取引報告書を自分で作るか、証券会社に作ってもらうかにありますが、特定口座のメリットはそれだけに留まりません。
前のページである「特定口座と一般口座の違い」では一般口座と特定口座を比べた上で「普通に使うなら一般口座はあまりメリットが無い」と書いたように、できる限り特定口座で開設するべき。では具体的に特定口座にするとどういったメリットがあるのでしょう?
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の2つが存在しますので、ここではこの2つの具体的なメリットデメリットに言及していきたいと思います。
特定口座とは?
源泉徴収ありとなしについて詳しく取り上げる前に、まず特定口座について簡単に説明しておきましょう。
特定口座には「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があると説明しましたが、どちらにも共通するのが証券会社の方で「年間取引報告書」を作成し、翌年1月末までに郵送してくれるという事。
株式投資は年間利益が20万円を超えると確定申告をする必要があり、その際に必要になるのが取引毎の損益や手数料、金利、貸株料などを記載した年間取引報告書です。
一般口座ではこれを自分で作成する必要がある一方、特定口座では源泉徴収のありなしにかかわらず証券会社が作成してくれるため、私たち投資家はそれをもとに確定申告を行えばいいだけ。
仮に年間の利益がマイナスだった場合は、年間取引報告書をもとに確定申告を行うことで損失の繰越控除を受けられ、翌年含め3年間は損失分だけ税金が非課税になります。
利益が出ても損失が出ても年間取引報告書があると手間が大きく省ける…それが特定口座の大きな特徴になっています。
特定口座「源泉徴収なし」の特徴
ではここから特定口座の源泉徴収ありとなしの違いを見ていきます。違いに関してはその名の通り証券会社が源泉徴収をしてくれるかどうかなのですが、色々とメリットデメリットがあります。
では「源泉徴収なし」から見てみましょう。
特定口座の源泉徴収なしは簡単かつ乱暴に言ってしまうと、証券会社が年間取引報告書を作成してくれる一般口座といった位置付けになります。
年間利益が20万円を超えると一般口座では年間取引報告書を自分で作成して確定申告を行う必要がありますが、特定口座の源泉徴収なしであれば証券会社がこの報告書を作成し1月末までに郵送してくれるので、それを使って確定申告を行えばいいだけ。
デイトレーダーなど膨大な数の取引を行う人間が年間取引報告書を作成すると恐ろしいほどの手間がかかるのは想像に難くありません。
年間利益が20万円未満なら報告書を使わなければいいだけの話ですし、トータルでマイナスになった場合は年間取引報告書をつかって確定申告することで損失の繰越控除を受けられます。
後述する源泉徴収ありのように、年間利益20万円未満であった場合に税金の払い損がないなどのメリットもありますので、少額投資なら源泉徴収なしのほうが良いケースが多くなるでしょう。
ちなみに、特定口座の源泉徴収なしに対して一般口座のメリットは何もありません。
特定口座「源泉徴収あり」の特徴
では次に特定口座の「源泉徴収あり」の特徴を見てみましょう。
まず、皆さん株の取引で利益が出た場合の税金についてはご存知でしょうか?
株取引の利益に掛かる税金というのは軽減税率が適用されていない限り一律で「利益の20.315%(所得税15.315%+住民税5%)」と決まっています。
「源泉徴収あり」の特定口座を選んだ場合、株の売買や配当などで利益が確定した時点で証券会社が自動的にこの20.315%を差し引きます。証券会社の方で納税までやってくれるので基本的に確定申告の必要はなく、とても楽です。
ただ、株取引に関わる利益の申告に関して年間の株の利益が20万円未満の場合は確定申告の必要はないというルールがあり、年間の利益が20万円に満たない場合は株の税金である約20%を払う必要はないのです。
じゃあ「源泉徴収あり」の特定口座で年間の利益が20万円未満だった場合は徴収された税金は戻ってくるのでしょうか?
答えはNOです。
源泉徴収ありでは税金の払い損も
では、それがどういうことなのか具体的に計算例を出してみます。
もし1年間の売買が1往復のみで、利益が18万円出たとします。
- 利益18万円×税率20.315%=源泉徴収額36,567円
…となり「源泉徴収あり」の特定口座だと自動的に18万円の利益から36,567円が引かれます。仮にこれが「源泉徴収なし」であった場合、年間利益が20万円未満に収まっているため、この税金は払う必要がありません。
しかし、源泉徴収ありの特定口座で徴収されてしまった税金は、年間利益が20万円未満に収まっていようが、確定申告をしようが返ってくるくることはありません。つまりこのケースでは36,567円の払い損ということになります。
「何そのふざけた仕組み」と感じるかもしれませんが、悲しいことにこれが特定口座の源泉徴収ありのルールなのでどうしようもありません。
損切りした場合は税金が戻ってくる
このルールを聞いた時、こんな疑問は生まれませんでしたか?「利益を確定するたび自動的に税金が引かれるなら、損切りした時の税金の扱いはどうなるんだ?」と。
損切りをすれば年間のトータル利益は減ることになるのですから、その分税金が戻ってこなければおかしいですよね。
株式投資において勝率100%などありえないわけですから、利益確定した時に20.315%引かれ、損切りの際に戻りがなかったとすれば、年間利益に対して税金の割合は30%、40%とどんどん高くなってしまうことになります。
結論から書くと、特定口座の源泉徴収ありの場合、損切りすればその分の税金は証券会社が戻してくれることになります。
先ほどと同じように1年間の利益を18万円と仮定し、今度は利益確定2回、損切り3回のケースで実際に見ていきたいと思います。
まず損益の内訳は…
- 1回目 +10万円
- 2回目 -3万円
- 3回目 -5万円
- 4回目 +21万円
- 5回目 -5万円
こういう取引を行った場合はどうなるかというと…
- 1回目 利益10万円×税20.315%=源泉徴収額-20,315円
- 2回目 損失3万円×税20.315%=源泉徴収戻り+6,095円
- 3回目 損失5万円×税20.315%=源泉徴収戻り+10,157円
- 4回目 利益21万円×税20.315%=源泉徴収額-42,661円
- 5回目 損失5万円×税20.315%=源泉徴収戻り+10,157円
こういう計算となり、トータルで結局36,567円の源泉徴収額となります。つまり年間に複数の取引を行った場合、損失が出た際には源泉徴収された金額から差し引きで税が戻ってくることになるのです。
注意して欲しい点は、損失が出てもその損失分まるまる戻ってくるわけではないということ。「前回の利益で4万円源泉徴収され、今回3万円損切りしたから、源泉徴収分の4万円で損失が埋められる」ということにはなりません。
戻り分は利益から3万円失われることによって減る源泉徴収分6,095円だけなので、そのへんは間違わないようにして下さい。
源泉徴収ありだからといって過剰に課税されることはなく、利益が出たら源泉徴収され、損失はそのまま…と思っていた方は安心して下さい。
ただ、一般口座や「源泉徴収なし」の特定口座なら年間利益20万円未満の場合引かれなくてすむ税金が、前線徴収ありでは払い損という事に変わりはありませんが…
源泉徴収ありは確定申告の必要がない
「年間利益20万円未満の場合税金の払い損が発生する源泉徴収ありはメリットないじゃん」と感じる人もいるかもしれませんが、決してそうではありません。
源泉徴収ありが最も力を発揮するのは年間利益が20万円を超えたケースなのです。
前述のように特定口座の源泉徴収ありはどんなに利益が多くても確定申告の必要がありません。これは「面倒な確定申告の手間が省ける」というメリットだけではなく、収入としてカウントされないという大きな強みがあるのです。
そのため、配偶者の扶養に入っているような人でも扶養から外れることはありません。仮に株で1億円稼いだとしてもです。
また、源泉徴収なしや一般口座では年間利益が20万円を超えると確定申告の必要があり、それによって収入が増えたと見なされ健康保険料が増額されてしまいますが、源泉徴収ありではそういったこともありません。
収入が一定額以下で適用される優遇などもそのまま受けることができるなどメリットは多く、年間利益が20万円を超える見込みがある人は、万が一20万円未満で税金の払い損が発生したことを考慮してもなお源泉徴収ありが良いでしょう。
さて、長々と特定口座について書いてきましたが、「結局どの口座が一番いいんだ?」とお悩みの人もいることでしょう。
次のページでは一般口座、特定口座の源泉徴収あり・なしの計3つの口座のメリットデメリットと最終的な結論を書いていきます。
あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
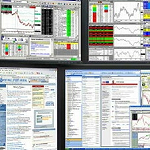
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
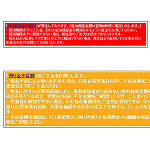
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む
