一目均衡表:雲の活用とねじれについて
一目均衡表で最も使用される「雲」
一目均衡表を語る上で真っ先に出てくるのが「雲」です。
アナリストなど投資の専門家が一目均衡表でのテクニカル分析を語る上で、まず持ち出してくるのがこの雲であり、基準線や転換線、遅行スパンといった線の使い方が分からなくても雲だけは分析に取り入れているという人も多くなっています。
多くの人が用いているということは、それだけ値動きに反映されやすい事を意味していますので、現在値が雲に絡む状況にある場合は積極的に用いるべき指標。主な使い方について必ず覚えておきましょう。
雲は支持線や抵抗線として強く作用する
では実際に一目均衡表の雲の使い方を見てみましょう。
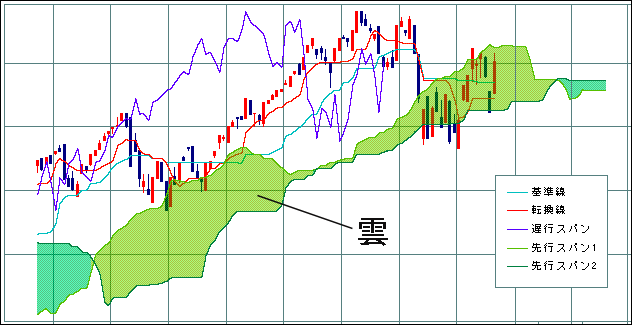
「この画像何回使うんだよ…手抜きすぎだろ…」というツッコミにもめげずに3度目の登場になる上の画像を見てもらうと分かるように雲は先行スパン1と先行スパン2に挟まれた領域を指し、上でも書いたように一目均衡表について詳しくない方でも「雲」という言葉は聞いた事あるのではないでしょうか。
雲の一般的な使い方として一番簡単なものに「ローソク足(現在値)が雲の上か下かで相場の強さを測る」というものがあります。
雲を形成している先行スパンは抵抗帯や支持帯としても機能するので、現在値が雲の上にあるのであれば、雲はトレンドラインでいう支持線的な役割を果たし相場を下支えする一方、現在値が雲の下にある場合は逆に雲(先行スパン)が抵抗線となります。(下図の黒い○)
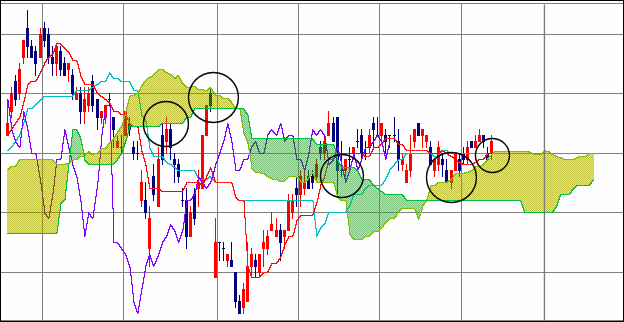
雲は抵抗帯として機能するが故に、一度雲を上抜ければそれだけ相場に勢いがある事になるので上昇トレンドに入る場合が多いですし、雲を下抜ければ売り圧力が強い事を意味し、下降トレンドに移行する事が多くなります。
現在値が雲の中にある場合は相場に迷いが見られ、雲を上抜くのか下抜くのか注視する必要があるのですが、不安定な事に変わりはないので雲の中に入ったら現在保有している株を一度決済してしまうのも一つの手になります。
雲は厚いほど支持線、抵抗線として機能する
雲を見てみると分かると思いますが、厚みが刻一刻と変化していますよね。
雲は厚みがあるほど…つまり先行スパン1と先行スパン2の間が広いほど抵抗帯や支持帯としての機能は強くなり、逆に雲が薄い場合は簡単に抜けやすくなる傾向が。
しかし雲が厚かろうが薄かろうが抜ける時はアッサリ抜けてしまうのであくまでも参考程度と思っておいて下さい。
そして一目均衡表の話をする上でたびたび話題になる「雲のねじれ」についてですが…
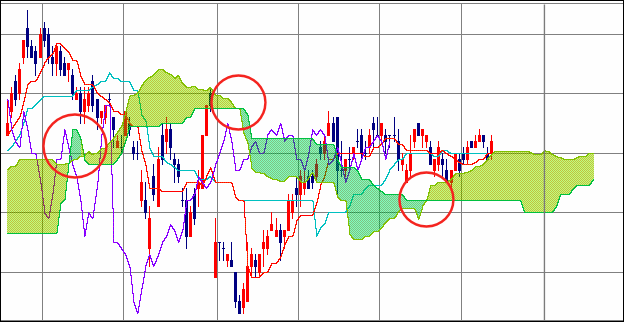
上図の赤丸の部分は先行スパン1と先行スパン2が交差する場所で「雲のねじれ」と呼ばれます。相場の転換点や変化日になるという話も聞きますが、上図を見ても雲のねじれが相場に影響を与えているようには見えませんし、実際大した影響はないというのが私の個人的見解です。
まあ、ねじれた部分周辺は雲も極限まで狭くなっているので抵抗帯・支持帯として弱くなる傾向にあり、雲の上抜けや下抜けが発生しやすいという意味で転換点にになりやすいのかもしれませんが…。
実際のチャートに当てはめ雲の働きを見る
上に載せたチャートを見ても、雲が支持線や抵抗線として機能している事、いったん抜けるとトレンドが形成されることが見て取れると思いますが、ここでは比較的新しい日経平均株価のチャートを用いて雲の働きを見てみましょう。
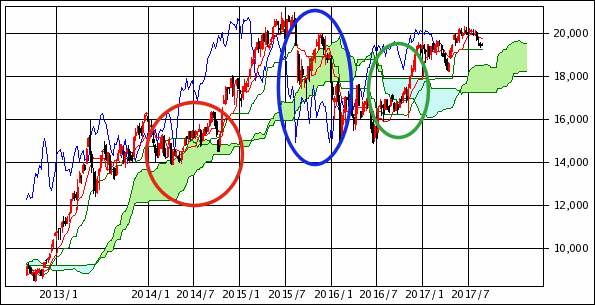
これは2012年11月に当時の与党民主党が解散総選挙にうって出て12月に自民党が大勝、アベノミクスが始まった直後からのもので、2014年にかけて急騰しているのが見て取れると思います。
2014年になって失速した株価は赤〇の部分で雲の上限に接触するものの、半年ほど雲の上限付近を転がった後一時上昇、その後急落して雲に突っ込むも、下抜くことなく再び雲を上抜き、そこから2015年半ばまで急騰しています。
次に青○を見てもらうと、2015年後半に入って急落し再び雲の上限での攻防後、年末から2016年初めにかけ急落して雲を一気に下抜いています。雲の下に現在値があるうち相場関係者も積極的に買いづらい状況ですので、しばらくは低迷が続きます。
しかし、緑〇付近になると、雲が徐々に下がってきたのとタイミングを同じくして雲に突入、そこから一気に駆け抜けて雲を上抜いた後は急騰し現在に至る。
このように、雲は支持線、抵抗線として強く作用しつつも、どちらかに抜ければその勢いのまま上昇あるいは下落する傾向にあるのです。
多くの人が参考にする雲は分析に極めて有用
過去のチャートを当てはめているので結果論と言われればそれまでですが、テクニカル分析というのはか勝率を少しでも高めるためのもの。多くの人が参考にする雲の存在は市場の動向を探る上で重要になるのは言うまでもありません。
相場を作り出しているのは人。その大多数が雲を意識すれば、セオリー通りの動きになる可能性が高まる結果に。プロの多くが移動平均線と並んで一目均衡表をよく利用するのは投資家心理を考えているからこそ。
ただし、雲を使った分析は比較的単純なので多くの投資家が簡易の分析法として用いており、故に相場の心理面でも有効ですが、本来一目均衡表は雲を含め基準線の向きや転換線との位置関係、遅行スパンと現在値の状況などトータルで分析するものなので、雲だけの分析はあくまでも一つの目安として参考程度に利用して下さい。
一目均衡表の雲と同様に世界中の投資家が使用する移動平均線を用いた分析を併用すると、より相場の動きを掴みやすくなるか。自分なりの上手な活用法を模索し確立するようにして下さい。
では次のページから基準線や転換線について詳しく解説していきます。
あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
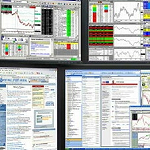
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
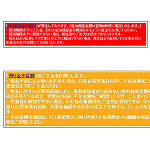
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む
