支持線と抵抗線の活用2
前ページでは主にトレンドラインやチャネルラインを用いた支持線、抵抗線について書いてきましたが、今度は移動平均線を用いた支持線、抵抗線について書いていきます。
移動平均線を使った支持線、抵抗線の場合、トレンドラインやチャネルラインのように自分で線を引く必要が無く、証券会社などで提供されている簡易なチャートだけで運用できるというメリットがあります。

上記は日足のチャートで、黄緑の線は25日移動平均線です。
この図では25日移動平均線が上値抵抗線として機能している場面が多くなっております。
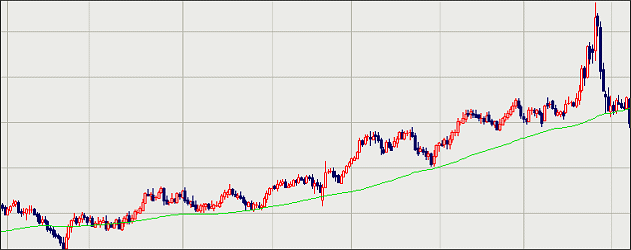
次は下値支持線で、上図は見事なまでに支持線の機能を果たしております。
ここで気になるのが何日の移動平均線を使えば良いのか?…という点でしょうか。
移動平均線を支持線、抵抗線として使う場合は長期移動平均線を使うのが一般的で、日足のチャートなら25日、75日、200日あたりです。
その3種類の中でも一番使われているのが25日移動平均線で、移動平均線を用いたテクニカル分析でも5日と25日の移動平均線が多く用いられている事を考えれば、まあ妥当でしょう。
75日や200日の移動平均線を用いる場合は長期的にどうこうというより、「25日移動平均線を抜けて、次の目安は75日移動平均線なる」といったような、短期的な支持、抵抗の目標を探る時に使う場合が多い印象を受けます。
もうひとつ気になるのは「トレンドラインを用いたものに比べて信頼性はどうか?」という点ですが、こればっかりはケースバイケースで何とも言えません。
何となく「トレンドラインは自分で引くという手間がかかる分信頼性は高い」というイメージはありますが、移動平均線にはゴールデンクロス、デッドクロスという長期移動平均線を上(下)抜く時の有名な呼び方があり、これは「長期移動平均線を抜けるには力が要る事を示しており、裏を返せば長期移動平均線の支持線、抵抗線としての機能が確立されている」となります。
トレンドラインやチャネルラインでも移動平均線でも「同じ線が支持線、抵抗線として機能し続けている期間が長ければ長いほど信頼性は増す」という特徴があります。
それだけに一度ブレイクすれば大きく動く事にも繋がりますので、長い間支持線や抵抗線に阻まれている相場の場合はブレイクのタイミングを注意深く見ておくといいでしょう。
あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
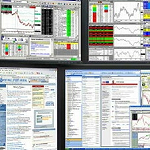
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
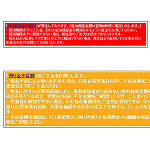
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む
