トレンドラインの引き方
株式投資を行う上で必ず必要となるのが株価チャートを用いるテクニカル分析。その中トレンドラインは基本中の基本といっても過言ではありません。
トレンドラインとは、相場の傾向や株価の転換点、心理的な支持線や抵抗線から下値や上値のメドを読み取るために、株価や為替相場といったチャートに引く線のことです。
非常にとっつきやすい分析であるうえ、移動平均線や一目均衡表などと組み合わせ信頼性を高めることも可能であるなど、多くの投資家が使用している強みも。
ここではそんなトレンドラインについて詳しく取り上げていきます。
トレンドラインの引き方
では具体的にトレンドラインの引き方について見てみます。
とはいえ、「引き方」と言っても単純明快で、下値が切り上がる上昇トレンドでは安値と安値を結び、逆に上値が切り下がる下降トレンドにおいては高値と高値を結ぶことで完成します。
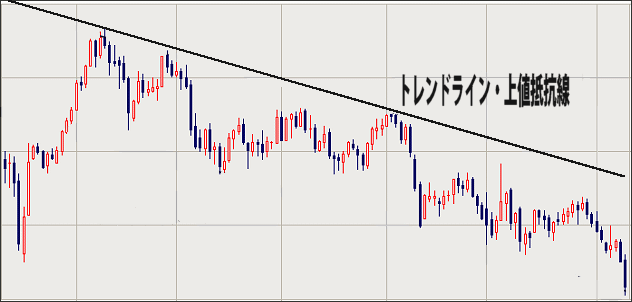
上図は下降トレンド時のトレンドラインを引いたもの。下降トレンド時は上値のメドやトレンド転換を読み取るため高値同士を結びます。
線を引くにあたってあまり神経質になる必要はなく、ある程度大雑把で構わない。
下降トレンドでのトレンドラインは上値抵抗線として機能し心理的に意識されるので、この抵抗線を上抜けるにはそれなりのパワーが必要になる場合が多くなります。ゆえに、下降トレンド時はトレンドラインに近づいた段階で売るのがセオリー。
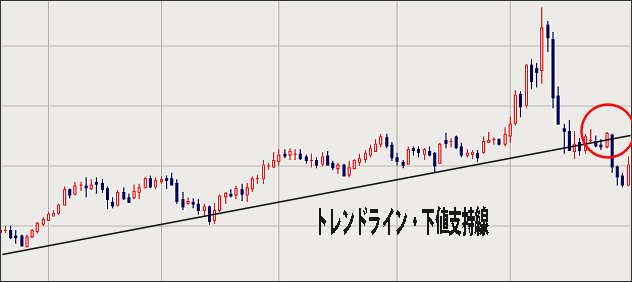
次に上昇トレンドでのトレンドラインです。
上昇トレンドの場合は下降トレンドの逆で安値同士をザックリと結びます。チャートの形によって多少はみ出ても問題ありません。
ただ、人によってははみ出ることを許容しない場合もありますし、どの程度まで許容するのかも人それぞれ。トレンドラインはある程度大雑把なメドを探るためのものなので、個人的にはあまり神経質になる必要はないかと。
上昇トレンドのトレンドラインは下値支持線として機能し、心理的に相場を下支えします。トレンドラインに近づいている状況は買いのサインということに。
ちなみに上図の赤丸で囲った部分は「ブレイク」といい、支持線を下抜いてこの上昇トレンドが終わったことを意味します。これについては後で詳しく解説していきます。
ヒゲは入れる?入れない?
トレンドラインを引く際、悩ましいのがヒゲの扱いではないでしょうか。
ヒゲを考慮するかどうかについては明確な規定はなく、ヒゲを含めるか除外するかは各々の判断に任せている感じ。
このあたりは状況によって異なる点でしょうか。ヒゲを含めたほうが綺麗なラインが引ける場合、ヒゲを含めない方がいい場合などがありますので、状況に応じてしっくりくる線を引くようにしてください。
場合によってはヒゲを含める・含めないによってラインの位置が大きく変わることも。そういったことを避けるためには自分なりのルールを設ける必要があります。
ちなみに、私は基本的にヒゲの先端を結ぶよう意識し、ヒゲの先端同士を結ぶとどうしても綺麗な線にならない場合はローソク足の実線を拾うこともある…という方法を用いています。参考までに
トレンドラインは基本中の基本
このトレンドラインは様々存在するテクニカル分析の中においても基本的なもの。多くの投資家が用いているからこそ市場ではこれが意識され価格形成に影響、それが信頼性を高める理由でもあります。
しかしトレンドラインを割り込んだからといって即座に「転換点だ!」と判断するのは危険です。
市場ではこのトレンドラインは比較的意識されるものの、何らかの材料で一時的大きく動くことによるオーバーシュートでラインを割り込み、再び値を戻すような「だまし」も多く存在するので過信は禁物なのです。
どんな高度なテクニカル分析でも絶対の信頼を置けるものなど存在しません。トレンドラインの他に世界情勢、相場の状況、ファンダメンタルズ、他のテクニカル分析なども考慮する必要があるのです。
とはいえトレンドラインが市場で意識されるのは間違いないありません。テクニカル分析というのは使用する投資家が多ければ多いほど市場心理に対する影響が大きくなり、その分析に沿った値動きになりやすいという特徴が。
そのため、移動平均線、ローソク足などと並んでもっとも基本的なトレンドラインは、積極的に使っていくべき分析法である点に疑いようはないでしょう。
では、次のページではもっと踏み込んだトレンドラインの使い方を解説していきます。
あわせて読みたい関連記事

信用取引は現物取引に比べ圧倒的に安い手数料が魅力のひとつです。しかし毎日金利や貸株料がかかるというデメリットもあり、「何日くらい保有すると現物より高くつくんだろう?」と考えたことはありませんか?その疑問に応えるべくいくつかのパターンで計算してみました…続きを読む

いざ投資をはじめようとした時「株にするかFXにするか」で迷う人は多いと思います。FXと株式投資どちらが儲かるかは人によって、もしくは投資法によって変わりますが、これらの特徴やメリットデメリットを詳しく解説しますので今後の投資に活かしてください…続きを読む

株価というのは良い材料が出れば上がり、悪い材料が出れば下がるとされています。しかし実際は全体の地合いやトレンドがものをいい、どんなに業績が良くても地合いが悪かったりトレンドが下降気味だったら株価は下がり、逆に業績が悪くても地合いが良ければ株価が上がる…続きを読む

株主優待をリスクなく貰う方法としていわゆる「優待タダ取り」というものがあります。厳密には手数料や貸株料がかかるためタダにはならないものの、銘柄を選べばかなりお得になります。しかし色々と注意点やデメリットもありますので損をしないための具体的な説明をしていきます…続きを読む
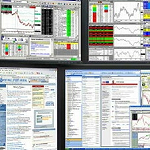
信用取引の場合2013年1月から差金決済が解禁され同一資金でいくらでも取引できるようになりましたが、現物取引の場合は差金決済が禁止されており同日中の同一資金による同一銘柄の取引は1往復までしか行えません。分かりやすく詳しい仕組みを見てみましょう…続きを読む
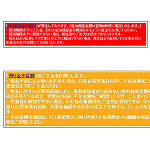
委託証拠金が不足し追証が発生しつつも、それを無視し期限を過ぎてしまったらどうなるのか?私自身が経験した追証から建玉を損切りしたものの結局信用取引を停止され、その後信用取引口座継続の意思確認を経て信用口座が復活した経緯を書きます…続きを読む

割安感を測る指標としてPER(株価収益率)は投資判断でよく用いられ、一般的に数字が低ければ「割安」とされますが、“マイナス”のPERはどうなのでしょうか?これは前期や今期予想などが赤字の場合に見られ、指標として意味を成しませんがV字回復への期待を込めて買うという方法も…続きを読む

株式投資とギャンブルの違いは胴元がいるかどうかもそうですが、やった後に何も残らないギャンブルと違い投資を始めると経済に敏感になり、結果経済の勉強になりますし、世界の人々が集う市場に参加するというのは閉鎖的なギャンブルの世界とは全く別物です…続きを読む
